普通の会社でもできるヘルスケア事業参入の秘訣#43 医療機器企業の研究開発ポートフォリオ管理
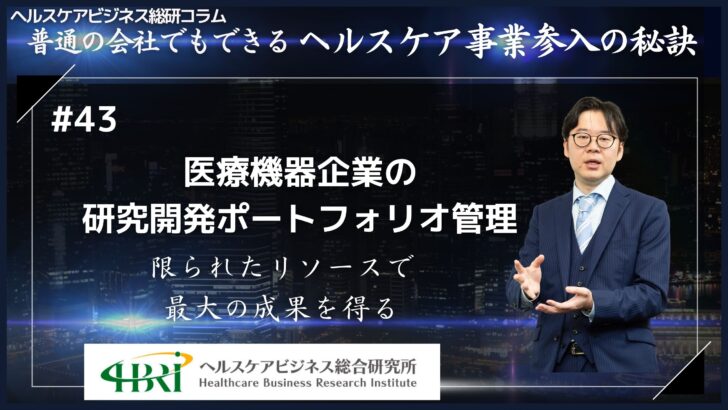
こんにちは、ヘルスケアビジネス総合研究所の原です。
「原先生、うちには色々な案件が持ち込まれるのですが、どれに投資すべきか判断に迷ってしまうんです。すべてに手を出すわけにはいかないし、どうやって取捨選択すればいいのか…」
これは先日、ある中堅医療機器メーカーの研究開発部長から受けた相談です。医療機器業界は他の産業と比べて研究開発投資の比率が高く、その成否が企業の将来を左右します。しかし、限られたリソースの中で、どのプロジェクトに投資するかという判断は非常に難しいものです。
特に昨今のように、技術の進化が加速し、市場環境や規制も目まぐるしく変化する中では、従来の感覚だけに頼った意思決定では立ち行かなくなっています。そこで今回は、医療機器企業における研究開発ポートフォリオ管理の考え方と、日本企業の現場で実践できるアプローチについてお話しします。
研究開発ポートフォリオ管理の重要性
研究開発ポートフォリオとは、企業が進めている、またはこれから取り組む可能性のある研究開発プロジェクトの集合体のことです。その管理とは、限られた経営資源(人材、資金、時間など)を最適に配分し、企業の経営目標達成に最大限貢献できるよう、プロジェクトの選定・評価・優先順位付けを行うことを指します。
医療機器産業の研究開発投資は増加傾向にあります。経済産業省の「医療機器産業実態調査」によると、2022年度の国内医療機器市場は4兆1,858億円となっており、研究開発投資も拡大しています。しかし、この成長市場で競争力を維持するためには、限られたリソースを効果的に配分する必要があります。
明確な評価の視点を持つ
プロジェクトを評価する際、欧米企業ではスコアリングによる定量評価が一般的ですが、日本企業では必ずしもそうした方法が定着していません。しかし、プロジェクトを評価する際の視点を明確にすることは重要です。
実務的な評価の視点としては「このプロジェクトは自社の強みを活かせるか?」「市場に真に求められているものか?」「薬事承認のハードルはどの程度か?」「収益化までの時間はどのくらいか?」「必要な投資規模は自社で対応可能か?」といった問いかけが役立ちます。
重要なのは、これらの視点をチェックリストとして形式的に使うのではなく、プロジェクトの本質を見極めるための「問い」として活用することです。定量評価が難しい側面も多いため、最終的には経営判断としての意思決定が求められます。
バランスの取れたポートフォリオ構築が成功の鍵
医療機器企業の研究開発ポートフォリオ管理で最も重要なのは、異なる性質のプロジェクトをバランスよく組み合わせることです。具体的には、次の3つのタイプのプロジェクトをバランスよく配置することが効果的です。
まず「短期的改良型プロジェクト」は、既存製品の改良や機能追加を目指すもので、比較的短期間(1〜2年)で成果が出やすく、リスクも低めです。既存の医療機器の使い勝手を改善したり、コストダウンを図ったりするプロジェクトが該当します。収益基盤を支える重要な取り組みですが、これだけでは長期的な成長は見込めません。研究開発ポートフォリオの中では、安定した収益を確保するため、このタイプのプロジェクトに一定の割合を割り当てることが一般的です。
次に「応用展開型プロジェクト」は、既存の技術やノウハウを新たな用途や市場に適用するものです。たとえば、循環器領域で使われていた技術を消化器領域に応用する、診断用機器のノウハウを治療用機器に展開するといった取り組みが該当します。
この応用展開型は、日本の医療機器企業にとって大きな課題となっている領域です。経済産業省の調査によれば、日本の医療機器産業は世界シェアで10%前後に留まり、特に治療系機器では5%程度と低迷しています。日本企業は技術力を持ちながらも、それを新たな市場や用途へ展開する際の戦略的アプローチや海外市場への展開力が弱いという課題を抱えています。既存技術の応用は技術的には可能であっても、規制対応や市場開拓の面で海外企業に後れを取っており、結果的に海外企業が大きな収益を上げている状況です。
最後に「革新型プロジェクト」は、全く新しい技術や概念に基づく製品開発です。成功すれば大きな成長が期待できる一方、リスクも高く、開発期間も5年以上かかることも少なくありません。AIやロボティクスを活用した次世代医療機器などが該当します。このタイプのプロジェクトには研究開発リソースの一部を計画的に配分することが重要です。日本企業の場合、単独でこのタイプのプロジェクトを推進するよりも、大学や研究機関との連携を通じて取り組むケースが増えています。
対話を重視した研究開発ポートフォリオ管理の実践
日本の医療機器企業の現場では、ポートフォリオ管理において対話を重視することが効果的です。形式的な管理手法よりも、経営層と現場の開発担当者が互いの考えを理解し合う風土づくりが成功の鍵となります。
ある中堅医療機器メーカーでは、社内新規プロジェクトを社長が主導でスタートしました。社長が方向性を示すまでは良かったものの、その後のコミュニケーションが不足していました。結果として、現場の担当者やマネージャーはトップの真意が理解できず動けない状態に陥り、一方でトップは現場からの情報が上がってこないため、どこに課題があるのか把握できないという状況に陥りました。これが採用や人材育成、ひいては事業成績にまで悪影響を及ぼしたケースがありました。
形式的な定期レビューを細かく設定しすぎると、かえって開発の自由度が失われ、プロジェクトが失速してしまうリスクもあります。大切なのは、経営層が明確なビジョンと方向性を示した上で、現場との双方向のコミュニケーションを維持し、プロジェクトの本質的な価値や課題について率直に対話できる環境を整えることです。
このような対話重視のアプローチにより、形式にとらわれない柔軟なポートフォリオ管理が可能になります。経営判断に必要な情報が適切に上がってくる一方で、現場は経営の意図を理解した上で、自律的に開発を進めることができるのです。
まとめ
医療機器企業における研究開発ポートフォリオ管理は、企業の持続的成長を支える重要な経営プロセスです。特に重要なのは、短期的改良型、応用展開型、革新型といった異なる性質のプロジェクトをバランスよく組み合わせることです。
冒頭の研究開発部長には、「完璧なポートフォリオを目指すのではなく、自社の強みを活かせる分野に集中し、定期的な見直しを通じて学習と修正を続けることが大切」とアドバイスしました。
医療機器業界は今後も技術革新と市場変化が続く中で、研究開発ポートフォリオ管理の重要性はますます高まるでしょう。皆様の企業でも、自社の文化や強みに合ったポートフォリオ管理の実践を通じて、限られたリソースから最大の成果を生み出す取り組みを進めていただければと思います。
このコラムでは医療・ヘルスケアビジネスに関係する情報やノウハウをお送りしています。面白かった記事やためになった記事は、ぜひご感想をお寄せください。最後までお読み頂きありがとうございました。