普通の会社でもできるヘルスケア事業参入の秘訣#58 「なぜ、うちの若手は育たないのか?」
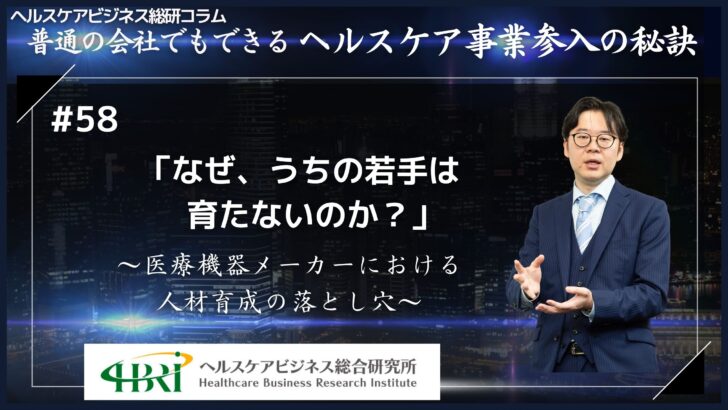
こんにちは。ヘルスケアビジネス総合研究所の原です。
先日、ある中堅医療機器メーカーの経営者の方とミーティングをしていた時のことです。「原さん、うちの若手がどうも育たなくてね。製品知識は誰よりもあるはずなのに、なぜか成果に結びつかないんですよ」と、深刻な表情で打ち明けられました。
これは、多くの医療機器・サービス企業が直面する根深い課題です。専門知識を持つ人材を採用すれば、すぐにでも現場で活躍してくれる「即戦力」になると期待しがちですが、現実はそう甘くはありません。
この問題の本質は、個々のスキルや知識の不足ではなく、もっと抽象度の高い「マインドセット」にあると私は考えています。今回は、小手先の育成テクニックではなく、若手が自律的に成長するために不可欠な、たった一つのマインドセットについてお話しします。
あなたの会社は「作業者」を育てていませんか?
若手育成で最も重要なこと、それは「顧客の課題を自分ごととして捉え、解決策を創造する」という当事者意識、いわゆるオーナーシップのマインドセットを育むことです。なぜなら、医療機器ビジネスとは、単に製品という「モノ」を売る仕事ではないからです。
顧客である医療従事者と共に、その先にいる患者さんのQOLをいかに向上させるかという共通のゴールを目指す、極めて専門性の高いパートナーシップが求められるビジネスなのです。
しかし、多くの企業では、育成の初期段階で製品知識や営業の型といった「やり方」ばかりを教えてしまいがちです。
その結果、顧客の言う通りに動くことはできても、「どうすればこの先生の課題を根本から解決できるだろうか」「この製品を通じて、病院全体の価値向上にどう貢献できるだろうか」といった、一歩踏み込んだ思考ができない「作業者」を育ててしまいます。これでは、急速に変化する医療ニーズや競合の激化に対応していくことはできません。
実際に、ある中小の医療機器メーカーA社では、臨床経験のある元看護師を営業担当として採用しました。彼女は製品のスペックや使い方については完璧に説明できます。しかし、医師から「この機能は、うちの病院の運用フローだと、かえって手間が増えそうだね」と指摘された際に、「そうですか」と引き下がるしかありませんでした。
彼女の頭の中には、製品を売るというミッションはあっても、顧客の課題を解決するというマインドセットが欠けていたのです。
「問い」こそが、人を育てる
では、どうすれば当事者意識というマインドセットを育むことができるのでしょうか。その鍵は、経営者や上司が若手に対して「答え」ではなく「問い」を与えることにあります。若手社員を、ただの実行部隊として扱うのではなく、事業を共に創るパートナーとして迎え入れ、思考させる機会を意図的に作ることが不可欠です。
例えば、若手の開発担当者に新製品のアイデアを考えさせる前に、まず担当領域の医療現場へ足を運ばせ、実際の業務を見学させる機会を設けることは非常に有効です。そこでのミッションは、単に業務の流れを覚えることではありません。
「自分が医療従事者だったら、今何に困るか?」「もし自分が患者だったら、どんな不安を感じるか?」といった問いを常に持たせ、現場の課題を徹底的に自分ごととして捉えさせることが重要です。こうした経験を通じて、教科書的な知識では得られない、生々しい課題意識が醸成され、それが革新的な製品開発の源泉となるのです。
また、経済産業省が主導した研究会の報告書によれば、従業員エンゲージメント(仕事に対する熱意や貢献意欲)と企業の業績には相関関係が見られることが指摘されています。特に、社員が自律的にキャリアを考え、挑戦できるような環境を整えることが、エンゲージメントを高め、ひいては企業の持続的な成長につながるとされています。
マインドセットを育むための仕組みづくり
当事者意識を育むことは、精神論だけでは実現できません。日々の業務の中に、自然とマインドセットが醸成される仕組みを組み込むことが重要です。例えば、営業の評価制度を見直してみるのは有効な一手です。
短期的な売上目標だけでなく、「顧客からどれだけ本質的な課題を引き出せたか」あるいは「解決策として、既存製品の枠を超えた提案を何回行ったか」といった行動そのものを評価項目に加えるのです。これにより、若手社員の意識は「売ること」から「課題を解決すること」へと自然にシフトしていきます。
最近では、個人の強みや情熱を業務に活かす「ジョブ・クラフティング」というアプローチも注目されています。これは、社員が自らの仕事の内容や範囲、人間関係を主体的に再定義していく考え方です。
例えば、データ分析が得意な営業担当者に、チーム全体の営業戦略立案に関わってもらうなど、トップダウンの指示ではなく、個人の「やりたい」というエネルギーを事業の推進力に変えていくのです。こうした取り組みは、「やらされ感」を払拭し、モチベーションと当事者意識を飛躍的に高める効果が期待できます。
医療機器・サービス企業の経営者の皆様に、今一度考えていただきたいのは、自社の人材育成が、未来のリーダーを育てるものになっているか、それとも単なる作業者を量産するものになっていないか、という点です。
若手にスキルや知識を教えることはもちろん重要ですが、それ以上に、彼らが自ら考え、行動し、失敗から学ぶための「環境」と「文化」を整えることこそが、経営者の最も重要な役割ではないでしょうか。企業の持続的な成長は、そうした土壌からしか生まれないのです。
参考文献
- 経済産業省, 「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書~人材版伊藤レポート~」, 2020年9月
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf - 独立行政法人 労働政策研究・研修機構, 「ジョブ・クラフティングの可能性の多角的検討」, 日本労働研究雑誌 2023年6月号
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2023/06/pdf/068-079.pdf