普通の会社でもできるヘルスケア事業参入の秘訣#57 社長1人で新規事業を始める時の立ち振る舞い戦略
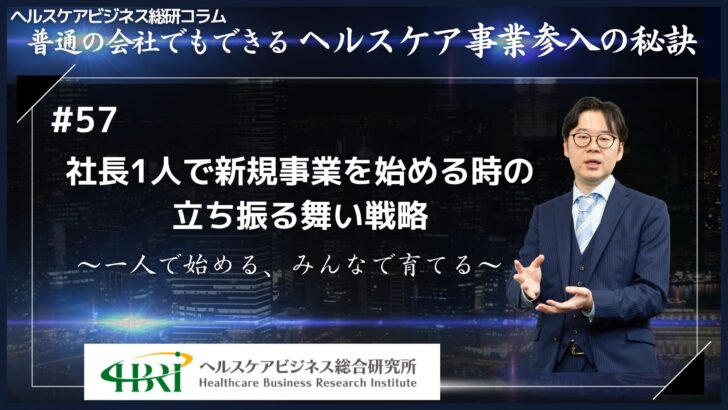
こんにちは。ヘルスケアビジネス総合研究所の原です。
今回は、ある医療機器のコーディネーターの方から伺った話です。
知り合いの医療機器メーカーの社長が、新しい医療機器の開発プロジェクトを立ち上げたいと考えていたそうです。ところが、社内のメンバーに相談したところ、みんな既存事業で手一杯で、新規事業に参加する余裕がないという反応だったとのこと。
その会社は中小規模で既存事業が好調だったため、社員の皆さんは現在の業務に集中したいという思いが強く、新規事業への参加には消極的だったようです。結局、その社長は一人で新規事業を始めることを決断したそうですが、実はこの「社員を巻き込まない」という選択は、戦略的に正しいかもしれません。その理由について、今日はお話ししたいと思います。
なぜ「社員を巻き込まない」という選択が正しいのか
経済産業省のデータをもとにした分析によると、新規事業の成功率は約29%、つまり約71%が失敗に終わっているという現実があります1) 。さらに別の調査では日本企業の新規事業の93%が失敗するという報告もあります 2)。
この高い失敗率を見ると、最初から多くの社員を巻き込むことのリスクが見えてきます。失敗の可能性が高い新規事業に優秀な社員の時間とエネルギーを割くことは、既存事業への悪影響を生む可能性があります。特に医療機器・医療サービス業界では、薬事法対応や品質管理など、既存事業でも高度な専門性が求められる業務が多く、そこから人材を引き抜くことは企業全体のパフォーマンス低下につながりかねません。
また、新規事業開発の専門家によると、事業創出の初期段階では「孤独との戦い」が避けられないといいます。経営者は元々孤独な立場にありますが、新規事業においてはその孤独をさらに深く受け入れることが、むしろ事業成功の鍵となるのです。
スモールスタートの威力と経営者の特権
最近の調査によると、スモールスタートで始めた新規事業の方が、大規模にスタートした事業よりも成功率が高いことが分かっています。特に医療機器・医療サービス業界では、医療現場のニーズが非常に細分化されているため、大規模な投資をする前に、本当にそのニーズが存在するのかを検証する必要があります3)。
社長一人で始めることの最大の利点は、意思決定の速さです。会議も根回しも不要で、思いついたらすぐに行動に移せます。医療機器開発では、医師との面談一つとっても、通常なら社内調整に数週間かかることがありますが、社長一人なら即座にアポイントを取って動けます。
さらに、経営者には社員にはない特権があります。それは、失敗しても社内で「なぜあんな無謀なプロジェクトに巻き込まれたのか」という不満が生まれないことです。この心理的な自由度は、大胆な挑戦を可能にします。
孤独な挑戦を成功させる実践的アプローチ
実際に社長一人で新規事業を進める際、「完全に一人」である必要はありません。外部のアドバイザーやコンサルタント、フリーランスの専門家など、必要に応じて外部リソースを活用することは可能です。固定費を増やさずに専門知識を得られるという点で、外部リソースの活用は理にかなっています。
社内には「社長の個人的な研究プロジェクト」として説明し、一部の若手だけに実際の作業を手伝ってもらって、正式な事業化の判断は試作品ができてからとする方法もあります。実際にこのような進め方で成功した企業も私は知っています。成功の可能性が見えてから社員を巻き込むという順序も、一つの賢明な選択です。
また、明確な撤退基準を設定しておくことも重要です。例えば、初期投資額の上限を決める、一定期間内に具体的な成果が出なければ撤退する、といった基準です。ある経営者は「個人の貯金から出せる範囲」を初期投資の上限と決めて、その範囲内で新規事業を試みたという話も聞きます。
タイミングを見極めて組織化へ
いつまでも一人で進めるわけではありません。ある程度の成功の兆しが見えたら、適切なタイミングで社内チームを編成する必要があります。
このタイミングの目安は「社長一人では物理的に対応できなくなったとき」です。引き合いが増えて商談が重なるようになった、試作品の改良サイクルが早くなって一人では追いつかない、といった状況です。
このタイミングで社員を巻き込む際のポイントは、すでに一定の成果が出ていることを示せることです。「社長が一人で頑張って、ここまで形にした。これからは皆の力を借りて大きくしたい」というストーリーは、社員にとっても参加しやすいものです。
まとめ
「社員を巻き込まない」という選択は、決して社員を信頼していないということではありません。むしろ、既存事業に集中してもらい、会社全体のリスクを最小化しながら、新たな成長の種を探るという、極めて合理的な経営判断なのです。
医療機器・医療サービス業界は、規制が厳しく、開発期間も長く、初期投資も大きくなりがちです。だからこそ、最初はスモールスタートで、社長自らがリスクを取って道を切り開くことに意味があります。
新規事業への挑戦を考えている経営者の皆様、まずは一人で小さく始めてみてはいかがでしょうか。その孤独な一歩が、会社の未来を大きく変える可能性を秘めているのです。
引用・参考資料
- https://www.consultancy-newbusiness.com/cousul_worries/failure.html https://kenja-succession.com/articles/innovation/success-rate/
- https://diamond.jp/articles/-/342310
- https://openhub.ntt.com/journal/8740.html https://tryx-co.ltd/new-business/how-to-start-small-in-a-new-business/