普通の会社でもできるヘルスケア事業参入の秘訣#56 医療関連企業こそ健康経営を
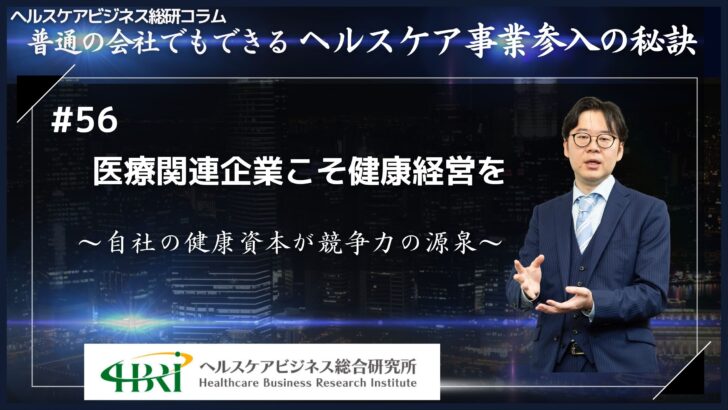
こんにちは。ヘルスケアビジネス総合研究所の原です。
先日、医療機器業界への新規参入を検討されている社長さんからご相談を受けました。「原先生、医療機器の市場に参入するにあたって、まず自社の従業員の健康管理をしっかりやらないといけないと思っているんです。でも、何から手をつけたらいいのか、どんな情報を集めたらいいのか、正直さっぱり分からなくて…」
このような悩みは、実は医療・ヘルスケア業界に参入しようとする企業、そして既に医療関連事業を展開している企業であっても、実際に直面する共通の課題です。
医療現場に貢献する製品やサービスを提供しようとする企業にとって、自社の健康経営は避けて通れない重要なテーマです。しかし、いざ取り組もうとすると、何から始めればよいのか途方に暮れてしまうケースが少なくありません。
なぜ医療機器・医療サービス企業にとって健康経営が重要なのか
健康経営という言葉は、最近よく耳にするようになりました。経済産業省の定義によれば「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」とされています。では、なぜ医療機器・医療サービス企業にとって、健康経営は特に重要なのでしょうか。
答えはシンプルです。医療・ヘルスケアビジネスは「健康」を扱うビジネスだからです。病院やクリニックに「健康になるための製品やサービス」を提供する企業が、自社の従業員の健康をないがしろにしていては、説得力がありません。
実際に、2024年3月に発表された「健康経営優良法人2024」の認定企業を見てみると、医療機器業界の大手企業が多数名前を連ねています。オムロンは「健康経営優良法人ホワイト500」に8年連続で認定され、富士フイルムホールディングスは2024年にはグループ28社が『健康経営優良法人2024』に認定されています(2024年7月現在)。
これらの企業は、自社の健康経営への取り組みを、顧客への信頼性向上と競争力強化の重要な要素として位置づけているのです。
健康経営に取り組む医療機器企業の現実
健康経営に積極的に取り組んでいる企業がある一方で、多くの中小規模の医療機器・医療サービス企業は、冒頭の社長さんのように「何から始めればよいのか分からない」という状況にあります。
その理由の一つは、医療業界特有の働き方にあります。医療機器の営業担当者は、病院やクリニックへの訪問、医療従事者との打ち合わせ、学会への参加など、外出や出張が多くなりがちです。また、医療機器の緊急対応やメンテナンスのために、不規則な勤務時間になることも少なくありません。
このような環境下で、従業員の健康管理をどのように行えばよいのか。一般的な健康経営の手法がそのまま適用できるのか。医療業界ならではの健康経営のあり方とは何か。これらの疑問に対する明確な答えが見つからず、多くの企業が健康経営への第一歩を踏み出せずにいるのです。
大手企業の取り組みから学ぶこと
では、健康経営に成功している医療機器企業は、どのような取り組みを行っているのでしょうか。
例えば、コニカミノルタは、全従業員を対象にストレスチェックを年2回実施し、産業医や外部の専門家によるカウンセリングを行っています。特筆すべきは、各組織長にストレスチェックの結果を共有し、高ストレスの部署には重点的に改善策を講じるという、組織全体でのアプローチです。
つまり健康経営は決して画一的なアプローチではなく、各企業の状況や課題に応じてカスタマイズされているということです。大切なのは、完璧な健康経営プログラムを最初から作ろうとすることではなく、自社の現状を把握し、できることから始めることなのです。
健康経営がもたらす意外な効果
健康経営の効果は、従業員の健康増進だけにとどまりません。医療機器・医療サービス企業にとって、健康経営は新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めています。
また、健康経営の取り組みは、営業活動においても強力な武器となります。「当社ではこのような健康経営を実践し、従業員の健康指標がこれだけ改善しました」という実績は、医療現場への提案において大きな説得力を持ちます。健康を提供する企業として、まず自社が健康であることを示すことができるからです。
さらに、健康経営優良法人の認定を受けることで、企業イメージが向上し、優秀な人材の獲得にもつながります。特に最近の若手人材は、企業の社会的責任や従業員への配慮を重視する傾向があるため、健康経営への取り組みは重要な差別化要因となります。
まず何から始めるべきか:情報収集という第一歩
ここまで健康経営の重要性や効果について述べてきましたが、冒頭の社長さんのように「何から始めればよいか分からない」という方も多いでしょう。そこで、医療機器・医療サービス企業が健康経営を始めるための最も重要な第一歩をお伝えします。
それは、「正しい情報収集から始める」ということです。
健康経営は一朝一夕に成果が出るものではありません。また、他社の成功事例をそのまま真似しても、自社に合わなければ意味がありません。まずは、自社の現状を正確に把握し、どのような健康経営が自社に適しているのかを見極めることが重要です。
例えば、以下のような情報を収集することから始めてみてはいかがでしょうか。
- 従業員の健康状態に関する基礎データ(健康診断の受診率、有所見率、残業時間、有給休暇取得率など)
- 同業他社や類似規模の企業の健康経営事例
- 外部の専門家による情報発信やアドバイス
特に3つ目ですが、産業医、保健師、健康経営アドバイザーなど、健康経営の専門家は数多く存在します。初期の段階で専門家のアドバイスを受けることで、効率的に健康経営をスタートできます。
おわりに
健康経営は、医療機器・医療サービス企業にとって、単なる福利厚生ではありません。それは、自社の信頼性を高め、競争力を強化し、新たなビジネスチャンスを生み出す重要な経営戦略なのです。
「健康を提供する企業」として、まずは情報収集から始めてみませんか。その小さな一歩が、やがて大きな成果につながるはずです。医療・ヘルスケアビジネスに携わる企業だからこそ、健康経営の価値を最大限に活かすことができるのです。
引用文献リスト
- 経済産業省 「健康経営とは」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html - 経済産業省プレスリリース 「『健康経営優良法人2024』認定法人が決定しました!」(2024-03-11)
https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240311004/20240311004.html - オムロン株式会社ニュースリリース 「『健康経営優良法人2024(ホワイト500)』に8年連続で認定」(2024-03-14)
https://www.omron.com/jp/ja/news/2024/03/c0314.html - 富士フイルムホールディングス サステナビリティサイト「社外からの評価」(2024年:グループ28社認定)
https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/evaluation - 富士フイルムグループ 『サステナビリティレポート2023』 p. 44(2023年:グループ36社認定)
https://www.fujifilm.com/files-holdings/ja/sustainability/report/2023/sustainabilityreport2023_two-page.pdf - コニカミノルタ株式会社 健康経営取り組み事例(PDF)