普通の会社でもできるヘルスケア事業参入の秘訣#55 中小企業が世界市場で勝つための「やらない戦略」
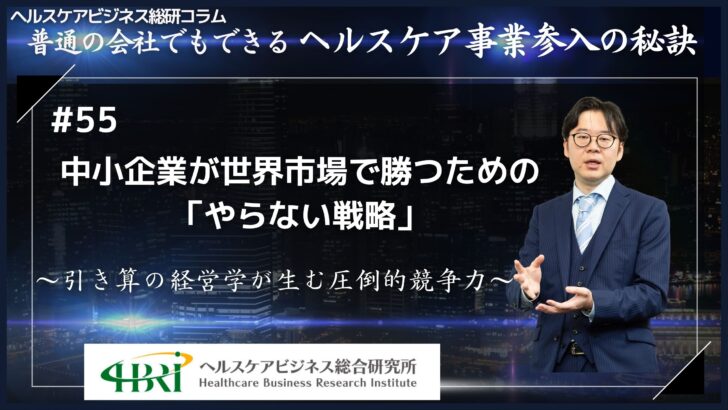
こんにちは。ヘルスケアビジネス総合研究所の原です。
先日、ある医療機器メーカーの経営者様とお会いしたときのことです。その方は、自社製品の営業で全国を飛び回っておられたのですが、ふと立ち止まってこんなことを仰いました。「原先生、うちの製品は技術的には競合他社に決して負けていないのに、なぜか市場シェアが取れないんです。もっと機能を高めて差別化を図るべきでしょうか?」
私は一呼吸置いてから、こうお答えしました。「社長、実は逆なんです。機能を高めるのではなく、何をやらないかを決めることの方が重要かもしれませんよ」。その経営者様は一瞬きょとんとされました。「やらない…ですか?」「ええ、そうです。実は世界シェア3割を超える、ある日本の医療機器メーカーがあるのですが、彼らの成功の秘密は徹底的に『やらないこと』を決めていることなんです」
経営者様の目が輝き始めました。「それは…どういうことでしょうか?」今日は、その答えについて詳しくお話ししたいと思います。
なぜ多くの企業が失敗するのか
医療機器ビジネスに限らず、多くの企業が陥る最大の罠は「あれもこれも」と手を広げてしまうことです。新しい技術が開発できたから別の分野にも応用してみよう、顧客から要望があったから新しい製品ラインを増やそう、競合他社が参入した市場だから自社も追随しよう…。こうした判断の積み重ねが、いつの間にか企業の強みを薄め、競争力を失わせていくのです。
特に医療機器業界では、この傾向が顕著に現れます。なぜなら、医療現場のニーズは実に多様で、「こんな機器があったら便利だ」という要望が次から次へと寄せられるからです。真面目な経営者ほど、これらの要望に応えようとして、結果的に自社の経営資源を分散させてしまいます。しかし、これこそが失敗への第一歩なのです。
世界で勝つ日本企業の「4つのやらないこと」
ここで、栃木県に本社を置くマニー株式会社の事例をご紹介しましょう。同社は手術用の針やナイフなどを製造する医療機器メーカーですが、驚くべきことに世界シェア3割強を誇っています。なぜこれほどの成功を収められたのか。その秘密は、同社が徹底している「4つのやらないこと」にあります。
第一に「医療機器以外は扱わない」。技術的には他分野への展開も可能でしょうが、あえて医療機器に特化することで、専門性を極限まで高めています。
第二に「世界一の品質以外は目指さない」。これは一見すると「やること」のように聞こえますが、実は「世界一以外の品質では満足しない」という意味で、中途半端な製品開発はやらないという宣言なのです。
第三に「製品寿命が短い製品は扱わない」。流行に左右される製品や、頻繁にモデルチェンジが必要な製品には手を出さず、長期間にわたって安定的に供給できる製品に絞り込んでいます。
第四に「ニッチ市場(年間世界市場5,000億円程度以下)以外は参入しない」。大手企業が参入してくるような大規模市場は避け、自社が優位性を発揮できる特定の市場セグメントに集中しています。
この「4つのやらないこと」により、マニー社は限られた経営資源を最大限に活用し、特定分野で圧倒的な競争力を築くことに成功しました。2008年には、この戦略が評価されてポーター賞を受賞しています。
自分の土俵を選ぶということ
マニー社の事例から学ぶべき最も重要な点は、「自分の土俵を明確に定義し、それ以外では戦わない」という決断です。これは企業規模や業界を問わず、すべての企業に当てはまる普遍的な原則です。
多くの企業が失敗する理由は、自社のアクセプタンスクライテリア(受け入れ基準)が曖昧だからです。どんな案件なら引き受けるのか、どんな市場なら参入するのか、どんな顧客なら対応するのか。これらの基準が不明確なため、目の前の機会に振り回されてしまうのです。結果として、あちこちに手を出しては中途半端に終わり、どの分野でも競争優位を築けないまま疲弊していきます。
成功する企業は、まず自社が勝てる土俵を明確に定義します。そして、その土俵の外から来る誘惑や圧力に対しては、どんなに魅力的に見えても「No」と言う勇気を持っています。これが「やらないことを決める」ということの本質なのです。
「やらない」ことがもたらす経営上の効果
「やらない戦略」を実践することで、企業には重要な変化が起きます。まず最も顕著に現れるのが、経営資源の集中投下による競争力の向上です。限られた人材、資金、時間を本当に重要な分野に集中できるため、その分野での競争力が飛躍的に高まります。これは単なる効率化ではなく、質的な変化をもたらすのです。
さらに、特定分野に特化することで専門性が深化していきます。その分野における知識、技術、ノウハウが蓄積され、他社が簡単には追いつけない優位性を構築できます。これは時間とともに強化される参入障壁となり、持続的な競争優位の源泉となるのです。
そして何より重要なのは、意思決定の迅速化です。「やらないこと」が明確になっていれば、新しい案件や機会が来たときの判断が早くなります。自社の基準に合わないものは即座に断ることができ、本当に重要なことに時間を使えるようになります。この判断の速さが、変化の激しい医療機器業界では決定的な差となって現れるのです。
なぜ「やらない戦略」を実行できないのか
ここまで読んで、「なるほど、やらないことを決めればいいのか」と思われた方も多いでしょう。しかし、実際にこれを実行するのは想像以上に難しいのです。なぜなら、ほとんどの日本企業は、そもそも最初の段階でつまずいてしまうからです。
問題の本質は、自社の強みや弱みを正確に把握する「棚卸し」ができていないことにあります。多くの経営者は「うちの強みは技術力です」「品質には自信があります」といった曖昧な認識しか持っていません。しかし、それでは「やらないこと」を決める基準が作れないのです。
実際、私がコンサルティングで関わった医療機器メーカーの多くが、この段階で行き詰まっていました。ある企業では、経営陣が集まって自社の強みを議論しましたが、各人の認識がバラバラで、結局「総合力が強み」という無意味な結論に至ってしまいました。別の企業では、競合分析を試みましたが、比較すべき軸が定まらず、分析が中途半端に終わってしまいました。
日本企業がこの棚卸しを苦手とする理由は、組織文化にも起因しています。「和」を重んじる文化では、自社の弱みを明確にすることは避けられがちです。また、過去の成功体験にとらわれて、現在の市場環境での自社の立ち位置を客観的に見られないケースも多いのです。
さらに深刻なのは、棚卸しの必要性すら認識していない企業が多いことです。「やらないことを決める」という発想自体が新しく、その前提となる自己分析の重要性が理解されていないのです。結果として、明確な方針を持たないまま、場当たり的な経営判断を繰り返すことになってしまいます。
棚卸しから始まる戦略構築
では、どうすればこの最初のハードルを越えられるのでしょうか。成功している企業の共通点は、外部の視点を活用していることです。自社だけで考えていても、どうしても主観的な評価になってしまいます。客観的な視点を持つ外部のコンサルタントや、異業種の経営者との対話を通じて、初めて自社の本当の姿が見えてくるのです。
また、棚卸しは一度やれば終わりではありません。市場環境は常に変化していますから、定期的に見直す必要があります。成功企業は、少なくとも年に一度は自社の立ち位置を再確認し、必要に応じて「やらないこと」のリストを更新しています。
この棚卸しができて初めて、「やらないこと」を決める土台ができます。そして、それを明文化し、全社で共有することで、組織全体が同じ方向を向いて進むことができるようになるのです。
医療機器ビジネスにおける「やらない戦略」の重要性
医療機器ビジネスにおいて、この「やらない戦略」は他の業界以上に重要な意味を持ちます。なぜなら、医療機器は薬機法などの厳格な規制を受けるため、新しい分野に参入するたびに莫大な規制対応コストがかかるからです。認証取得、品質管理体制の構築、市販後調査など、分野を広げるほどこれらのコストは雪だるま式に増えていきます。
また、医療現場のニーズは非常に専門的で、深い理解が必要です。循環器内科で使う機器と整形外科で使う機器では、求められる性能も使用環境も全く異なります。幅広い分野をカバーしようとすると、どの分野も中途半端な理解になってしまい、真に現場のニーズに応える製品開発ができなくなってしまうのです。
さらに重要なのは、医療機器は人の命に関わるため、メーカーへの信頼が極めて重要だということです。特定分野で長年の実績を積み重ねることで、その分野のスペシャリストとしての信頼を獲得できます。この信頼は一朝一夕には築けません。分野を絞り込み、その分野で圧倒的な存在感を示すことで、初めて医療現場から選ばれる企業になれるのです。
これは決して消極的な戦略ではありません。むしろ、自社の強みを最大限に発揮するための、極めて積極的な戦略なのです。限られた経営資源を最大限に活用し、特定分野で圧倒的な競争力を築く。これこそが、医療機器メーカーが世界市場で勝つための道筋なのです。
新規参入をお考えの企業様も、既に医療機器事業を展開されている企業様も、ぜひ一度立ち止まって「何をやらないか」を考えてみてはいかがでしょうか。自分の土俵を明確に定義し、その土俵で徹底的に戦う。それが、持続的な競争優位性を構築する第一歩となるはずです。皆様の企業が、日本の医療機器産業の新たな成功事例となることを、心から願っています。
引用文献
- ポーター賞「マニー株式会社 受賞企業・事業レポート」(2008年)https://www.porterprize.org/pastwinner/2008/12/02111040.html