普通の会社でもできるヘルスケア事業参入の秘訣#46異業種からのヘルスケア市場参入戦略
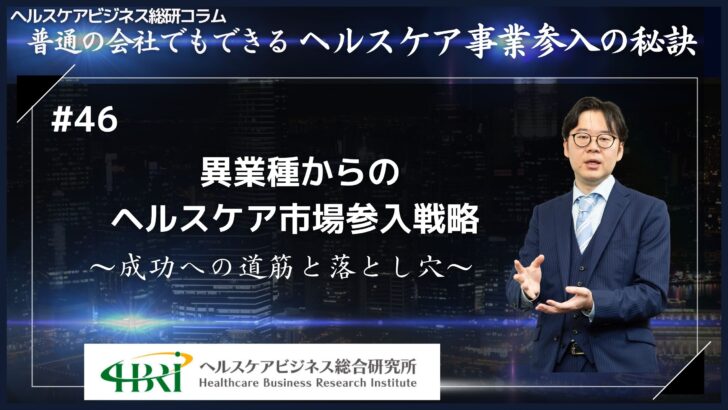
こんにちは、ヘルスケアビジネス総合研究所の原です。
「原先生、弊社でもヘルスケア事業への参入を検討しているのですが、何から始めればいいのでしょうか?医療機器の規制が厳しいと聞きますし、そもそも医療現場のことがよく分からないんです…」
先日、製造業の社長からこんな相談を受けました。確かに医療・ヘルスケアは成長産業として注目されていますが、参入ハードルの高さに躊躇される経営者の方も多いのではないでしょうか。
実は、ヘルスケア業界への異業種参入は年々増加しているものの、成功率は決して高くありません。PwC Japanの調査によると、国内企業の約7割がヘルスケア事業への参入意向を示す一方、実際に参入できているのは約2.5割にとどまっています(2024年3月時点)。その差はどこから生まれるのでしょうか?
今回は、異業種からヘルスケア市場に参入する際の戦略について、前提知識がなくても理解できるよう解説します。
ヘルスケア市場の魅力と成長性
まず、なぜ多くの企業がヘルスケア市場に参入しようとしているのかを理解しましょう。
経済産業省の推計によれば、国内のヘルスケア産業は2025年には約33兆円、2050年には77兆円規模に成長すると見込まれています。高齢化社会の進展、医療・健康への関心の高まり、テクノロジーの発展により、この市場は今後も確実に拡大していくでしょう。
特に注目すべきは、従来の医療機器や医薬品だけでなく、健康管理サービス、予防・未病対策、医療IT、在宅医療支援など多様な分野へと拡大していることです。これにより、製造業、IT、小売、サービス業など様々な業種からの参入機会が生まれています。
しかし、市場の大きさに惹かれるだけでは成功することはできません。参入の前に、業界特有の構造や課題を理解する必要があります。
ヘルスケア市場参入の障壁と課題
ヘルスケア業界、特に医療機器分野での最も大きな参入障壁は「規制対応」です。医療機器は人の生命や健康に直接関わるため、厳格な安全基準や品質管理が求められます。
医療機器の製造販売には、「製造業許可」「製造販売業許可」が必要であり、製品によってはクラス分類に応じた「承認」や「認証」の取得が必要です。また、GMP(製造管理及び品質管理の基準)やQMS(品質マネジメントシステム)といった製造・品質管理の体制も求められます。これらの規制対応には、専門知識だけでなく、時間とコストがかかります。
次に大きな障壁となるのが「医療現場理解の難しさ」です。医療現場は一般企業とは異なる独自の文化や価値観を持っています。意思決定プロセスも特殊で、医師、看護師、技師、事務といった多様な職種が関わり、最終決定者が誰なのかが分かりにくいことも少なくありません。
三つ目の障壁が「販路開拓の難しさ」です。医療機器の販売には特殊な流通チャネルがあり、既存の商流に入り込むのは容易ではありません。また、医療現場での新製品導入には慎重な検証プロセスがあり、導入までに時間がかかることも多いです。
最後に「投資回収の長期化」も課題です。開発から承認取得、市場導入までに3〜5年以上かかることも珍しくなく、初期投資の回収に時間がかかります。
こうした障壁があるからこそ、多くの企業が参入に二の足を踏むのですが、戦略的なアプローチで乗り越えることは可能です。
異業種参入の成功事例
では、実際に異業種から成功裏にヘルスケア市場に参入した企業の事例を見てみましょう。
カメラメーカーのオリンパスは、レンズ技術を活かして内視鏡分野に参入し、現在では世界シェアトップクラスのポジションを獲得しています。同様に、キヤノンも画像処理技術を応用して医療機器分野に参入し、眼科や放射線診断機器で成功を収めています。
一方、オムロンは血圧計などの健康機器から始め、現在では幅広いヘルスケア製品・サービスを展開しています。同社の成功の鍵は、自社のセンシング技術を活かした製品開発と、段階的な市場拡大戦略にあります。
富士フイルムは、写真フィルム事業の縮小に対応するため、画像処理技術を医療分野に応用し、X線画像診断システムなどで新たな成長を実現しました。
これらの企業に共通するのは、自社の強みを活かせる領域から参入し、段階的に事業を拡大していった点です。いきなり高度な医療機器から始めるのではなく、自社の技術やノウハウを活かせる領域から着実に実績を積み上げています。
成功のための重要ポイント
最後に、ヘルスケア市場参入を成功させるための重要なポイントをいくつか挙げておきます。
医療現場のニーズを深く理解する
製品開発の出発点は、医療現場の真のニーズを理解することです。技術起点ではなく、ニーズ起点の発想が重要です。そのためには、医療従事者とのコミュニケーションを積極的に行い、現場の課題や要望を直接聞くことが大切です。
経済産業省のレポートによれば、医療機器開発の失敗理由の上位に「現場ニーズの誤認」があります。どんなに優れた技術でも、現場のニーズに合致しなければ採用されません。
パートナーシップの構築
ヘルスケア業界は専門性が高く、単独での参入は困難です。医療機関、研究機関、医療機器メーカー、流通業者など、様々なステークホルダーとのパートナーシップ構築が成功の鍵となります。
特に医療機関との連携は重要で、製品開発の初期段階から医師や看護師の意見を取り入れることで、使いやすく効果的な製品を開発できる可能性が高まります。
長期的視点と経営者のコミットメント
ヘルスケアは参入や成長にも時間が掛かりますし、一旦売れ出すと十年以上、ずっと売れ続けることもあります。したがってITのように短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点で取り組む必要があります。特に医療機器の場合、開発・承認・市場導入には長い時間がかかるため、経営者の強いコミットメントが不可欠です。
実際、PwCの調査によるとヘルスケア事業で成功している企業の共通点として「経営者の長期的コミットメント」が挙げられています。短期的な利益よりも、社会的価値と持続的成長を重視する姿勢が求められます。
専門人材の確保と育成
ヘルスケア事業を進める上で、医療や薬事に関する専門知識を持つ人材の確保・育成は欠かせません。特に薬事法規制に精通した人材は、スムーズな製品開発と承認取得のために重要な役割を果たします。
最初は外部コンサルタントの活用も有効ですが、長期的には社内に専門知識を蓄積することが望ましいでしょう。
まとめ
ヘルスケア市場は大きな成長可能性を秘めていますが、参入には独自の障壁と課題があります。しかし、自社の強みを活かし、段階的にアプローチすることで、異業種からでも十分に成功の可能性があります。
重要なのは、医療現場の真のニーズを理解し、パートナーシップを構築しながら、長期的な視点で取り組むことです。また、規制対応を単なる負担ではなく、製品の安全性と品質を保証するための仕組みとして前向きに捉えることも大切です。
最後に強調したいのは、ヘルスケア事業は単なるビジネスチャンスではなく、社会的課題の解決に貢献できる領域だということです。人々の健康や生活の質向上に寄与する製品・サービスを提供することは、企業の社会的価値を高め、持続的な成長につながる可能性を秘めています。
新規事業をお考えの経営者の皆様、ぜひヘルスケア分野への参入を検討してみてはいかがでしょうか。本記事が皆様のビジネス展開の一助となれば幸いです。
ご意見やご質問がございましたら、ぜひ弊社ウェブサイトやX(Twitter)からお寄せください。
参考資料
- 「ヘルスケア事業新規参入に関する企業意識調査」PwC Japanグループ
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/healthcare-business.html - 経済産業省「ヘルスケア産業政策」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/index.html